こんにちは。
みなさん毎日お仕事お疲れさまです。
毎日仕事をしているみなさんが絶対に避けては通れないものがあります。
それは
同僚や上司、取引先にはいろんな性格の人がいますが、中にはマジで腹立たしい人もいますよね。
そんな人と毎日接しているとストレスが溜まってしまい、時には怒り狂って発狂しそうになります。
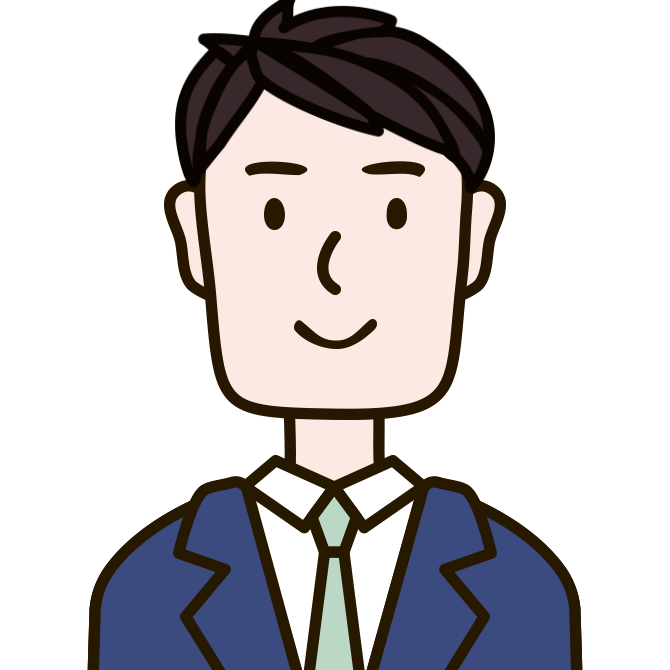
かくいう私も、現在仕事のストレスが限界に達しております。笑
そんな時、僕はこんな本を読みました。
「アンガーマネジメント」著者:戸田久実
|
この本を読んで学んだことは、
ということです。
怒りをコントロールすることで、イライラしたり不安になったりする時間が減り、自分のやりたいことに集中でき、毎日楽しく生活できるようになります。
ストレスを感じて過ごす時間程、無駄なものはありません。
「ストレス」「怒り」とは何なのか
そのコントロール方法はどのようなものなのか
整理していきましょう。
①ストレスはマジで体に良くない
「ストレスは体に良くない」と言われても
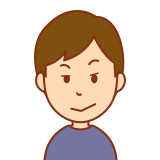
何を当たり前のことを言ってるんだ。そんなことわかってるわ。
と思う人が98%くらいを占めてると思います。
しかし、体に悪いとわかっていながらも、みなさんストレスを抱えて生活しています。
できる範囲でストレスを避け生活しているかとは思いますが、他人が要因でストレスを感じざるを得ない場合が大半だと思います。
ストレスを抱えていると、うつなどの精神疾患や高血圧、免疫機能の低下を引き起こす可能性があります。
また身体的な症状に加えストレスを懸念するもうひとつの理由は、ストレスが健康的な習慣を邪魔し、不健康な習慣が身に付いてしまう大きな要因になることです。
💡ストレス要因による不健康な習慣
・暴飲暴食
・飲酒
・喫煙
ストレス発散のために大食い、やけ酒、喫煙。
このような人は世の中に本当にたくさんいます。
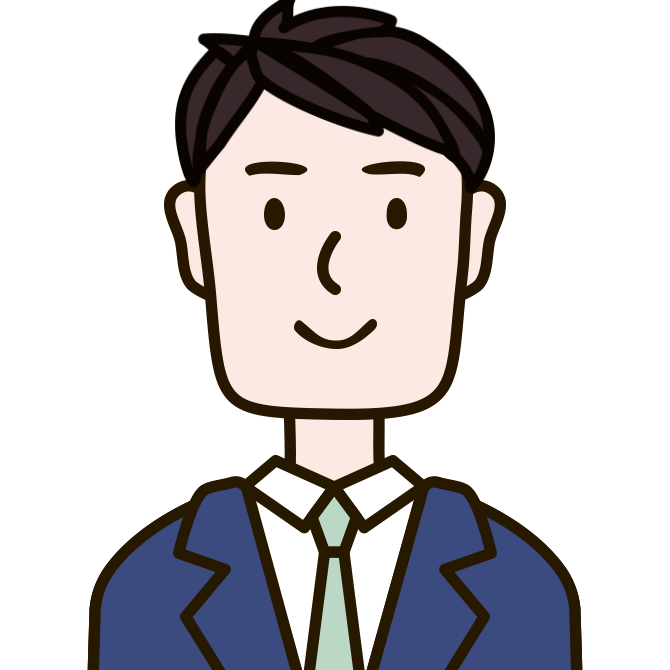
自分も20代のころはストレス発散のために酒、タバコ、ギャンブルに溺れていました。笑
ストレスは直接的に体に悪いのはもちろん、上記のような悪習慣が要因となり2次災害的に健康に悪影響を与えるものです。
②怒りの正体
怒りとは何なのか?
みなさん考えたことがあるでしょうか?
僕はありませんでしたが、パッと思いつくのは
正義感からくるもの
なんかあながち間違ってなさそうな感じですが、本を読んだところ怒りのメカニズムが書かれていましたので、紹介します。
1)怒りの裏側には感情がある
怒りの裏側には、不安、心配、悲しみ、虚しさがあり、怒りは第2次感情である言われています。
事例を挙げて解説します。
例)部下が何度言っても同じミスを繰り返す場合
上司が部下に「何度言ったらわかるんだ」とキレてます。
この時キレている上司の感情の裏側には、1次感情が潜んでいます。
「できると思って教えているのに、悲しい」
「できるように教えてあげられていない自分が、虚しい」
「この部下に今後も仕事を任せていいのか、心配」
このような1次感情を素直に表現できれば声を荒げて怒ることもないのですが、怒りのエネルギーの方が強いため、
「何やってるんだ!」
「いい加減にしろ!」
と、つい怒りの態度をとってしまう人が多いです。
怒りのパワーは喜怒哀楽の中で1番強いのです。
③ストレス、怒りはどんな時に感じるのか
ストレスや怒りはどんな時感じるのか。
社会人のみなさんは特に会社で、学生のかたは学校で感じると思います。
年代によって違うと思いますので、実際僕が感じていたストレスはこんな感じです。
1)僕が感じていたストレス
💡学校で感じていたストレス、怒り
・嫌なやつがいる
・怖い先輩に目を付けられている
・髪型がキマっていない
・先生により授業がつまらない
💡会社で感じていたストレス、怒り
・上司や得意先からの理不尽
・部下の成長が遅い
・言い方が超むかつくアホがいる
・仕事が雨のように降ってくる
・毎日残業・納期、期限に追われている
・電話ばかりきて仕事が進まない
2)価値観のズレがストレス・怒りを生む
常識や「〜すべき」という価値観は人それぞれ違います。
人に価値観を押し付けられるとむかつくしストレスがたまります。
逆に価値観を押し付けたくなる時も、イライラします。
電車などの公共機関では特に注意が必要です。
電車はいろんな人間が乗車し、価値観が違う人ばかりです。
電車内ではいろんな人を目撃します。
・周りを気にせず電話している人
・化粧をしている人
・ご飯を食べてる人
・聞いてる音楽が爆音でイヤホンから大きな音が漏れている人
・降りる人がいるのに先にズカズカ乗ってくる人
・吊り革で懸垂してる人
こんな人達を見ると、「イラっ」とします。
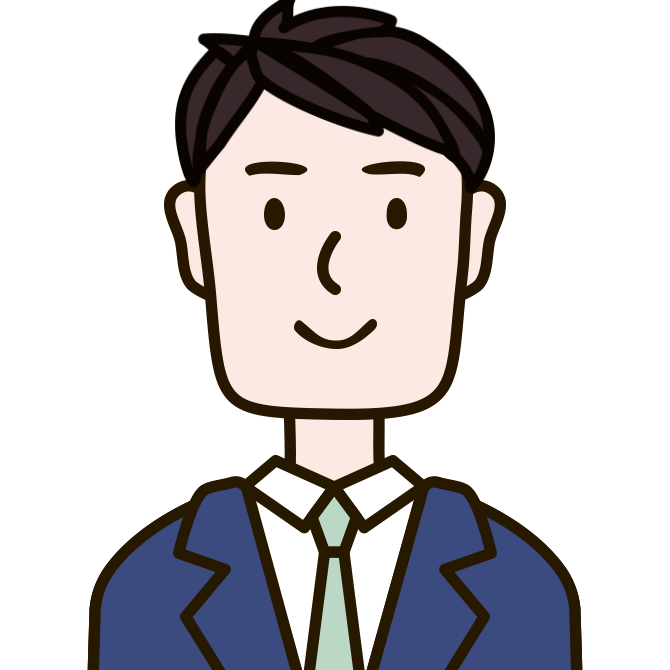
公共の場でなにやってんだよ💢
こう思います。
でも本人は、「人に迷惑を掛けていないから良い」と思っています。
この「価値観のズレ」が、怒りやストレスに直結してきます。
そしてこの価値観のズレは、そう簡単にはお互い理解し合えません。
3)身近な対象ほど怒りは強くなる
実は身近な対象に対しては、怒りが強くなる性質があります。
長く一緒に働いている職場の人、家族、友達など。
・長く一緒にいるのだから、このくらい言わなくてもわかるはず
・自分の思い通りに動いてくれるはず
・少しくらい感情的になっても許してくれるはず
このように思うようです。
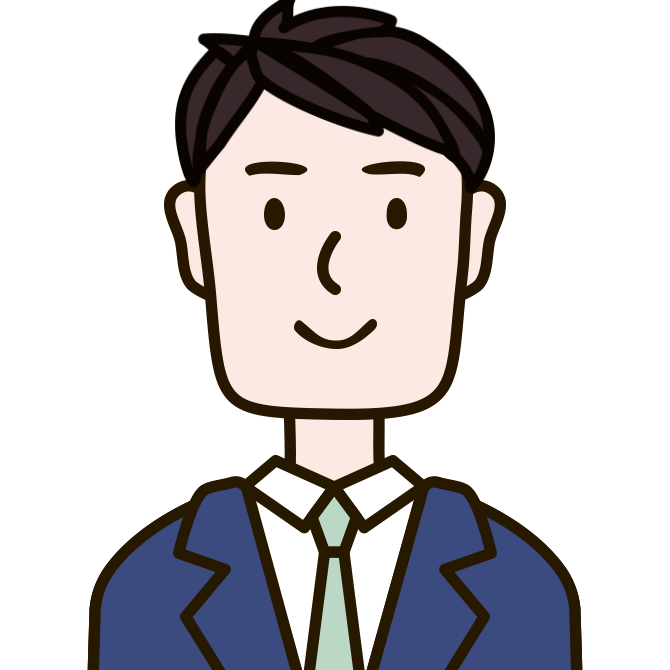
夫婦喧嘩なんかは一番わかりやすい例かもしれないですね。僕も3日に1回は奥さんと喧嘩してます。笑
この「身近な対象ほど怒りは強くなる」という特性を理解し、怒りやストレスをコントロールしていきましょう。
④怒りをコントロールする方法
怒りがどんなものなのか整理できたところで、
一番肝心な怒りをコントロールする具体的な方法を紹介していきます。
1)6秒我慢法
怒りが生まれてから、理性が働くまで6秒かかると言われています。
いくらむかついても、6秒経てば理性が怒りを上回り、怒りを鎮めてくれます。
とにかく6秒だけ我慢する。
そしたら勝手に理性が働きます。
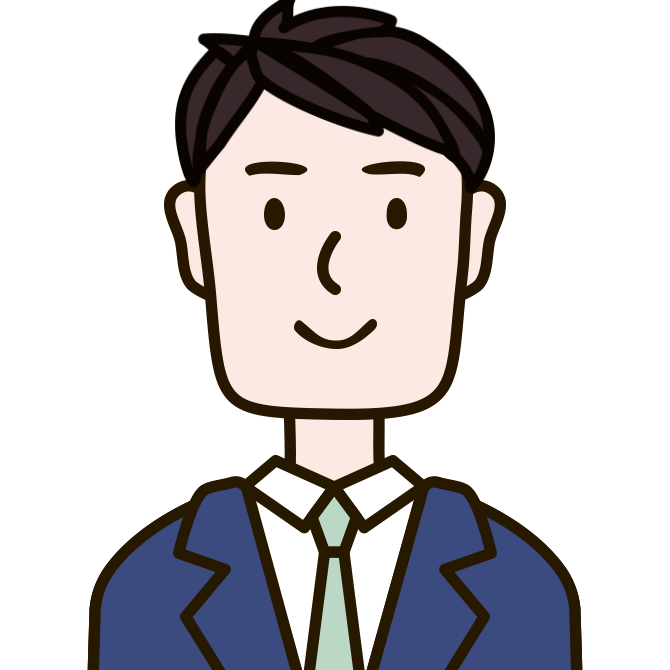
実際に会社でやってみたところ、最初の2秒くらいはきつかったのですが、3秒以降はだんだん怒りがおさまってきました。
2)深呼吸
むかつく出来事が起きたら、すぐに深呼吸しましょう。
やり方は、4秒吸って8秒はく。
ただこれだけ。
怒っている時は、交感神経優位になります。
深呼吸をするとことで、副交感神経優位になり心がリラックスします。
怒りのボルテージにより違いはありますが、30秒〜1分くらいやってみましょう。
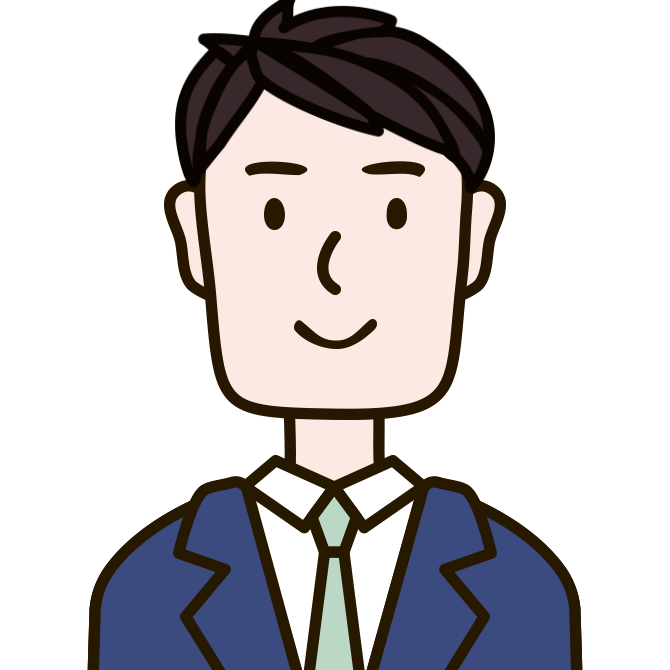
深呼吸している間に6秒たって理性が追いついてきますので一石二鳥です
3)怒り採点
その時感じた怒りを、瞬時に採点しましょう。(10点満点で)
怒りに点数をつけることは、考えること。
すなわち理性が働きます。
理性が働くと怒りはおさまりますし、採点したら意外と低かったとなると怒る気にもならなくなってきます。
0点 全く怒りを感じていない状況
1〜3点 イラっとするが、すぐに忘れる程度の軽い怒り
4〜6点 時間がたっても心がざわつく怒り
7〜9点 頭に血がのぼるような強い怒り
10点 絶対に許せない激しい怒り
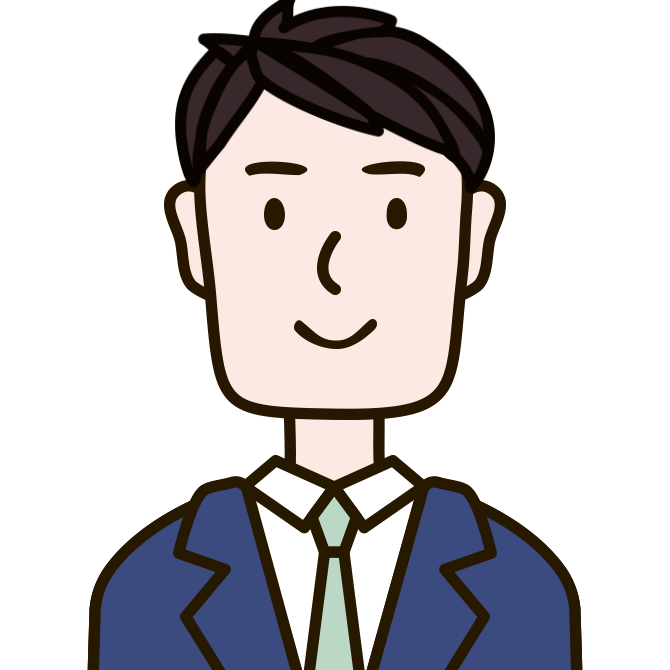
実際に自分も職場でやってみました。4〜6点くらいの怒りは「まあこの程度のことなら怒ることもないか」と思うことができました。7点以上の怒りは今のとこあまりないですね。
4)妄想する
妄想する。
ちょっとよくわからないかもしれないですが、別の言い方をすると、「違う視点で考える」ということです。
例えば怒っている上司を見た時、「あの怒ってる上司は家で奥さんにいつも怒られてるのかもしれない」と妄想してみましょう。
そう考えると、「家では奥さんに怒られっぱなし、もしかしたら子供にも嫌われていて家では居場所がないのかもしれない」と思い、なんだか可哀想と思ってしまいます。
そうすると、怒りの感情がなくなり、「仕方がない」と思えるようになります。
怒っている人を見た時、その人も本当に悪い人ではなく、私生活で色々な問題を抱えていたり、可哀想な境遇かもしれない。
このように妄想したり別の角度でその人を見ることにより、怒る気持ちがなくなる場合もあります。
5)考え方を変える
自分の価値観や考え方を柔軟に変えれるようにするといいです。

それができないから困ってるのですが。。。
まあ簡単ではないと思いますが、少しずつやってけば自然とできてきます。
他人は変えられない場合が多いので、自分が変わらなければいつまで経ってもつまらないことで怒ってしまうかもしれません。
なので自分で柔軟に考え方を変えるのです。
例えば僕の場合ですが、
言い方がきつい人が同じ職場にいます。
先輩ですが役職はついてなく、他の人からも嫌われています。
アスペルガー症候群の特徴があります。
みたいな感じで、なんでもかんでもいちいち自分の仕事に首を突っ込んできては、人をイラつかせるような言い方をしてきます。
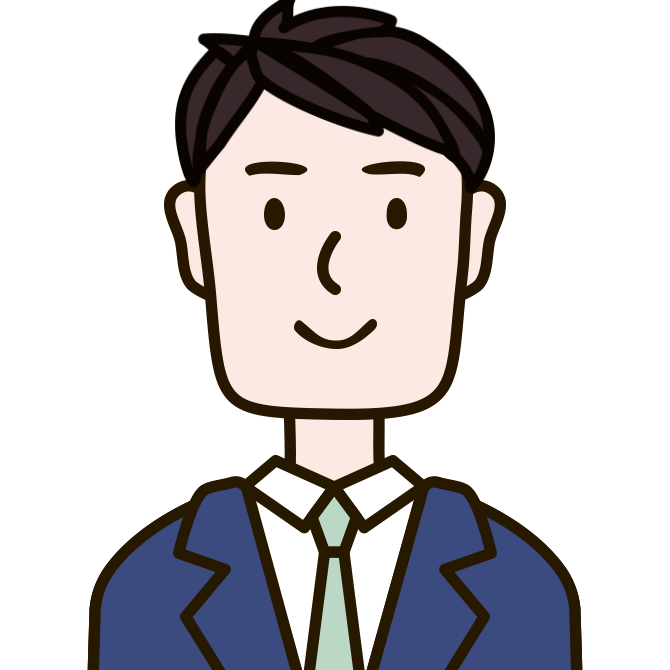
そのくせ自分はミスが多い。笑
一度は言い方について話しましたが、話しても治りませんでした。
その人は変わらなかったので、自分が考え方を変えました。
・この人は人とコミュニケーションをとるのが苦手。
・うまくコミュニケーションがとれると思ってる自分が悪い。
・コミュニケーションがとれない人という前提で接するようにしよう。
・いちいち首を突っ込んでくるのは優しさだ。
・この人は皆に嫌われているし、言うことにいちいち耳を傾けても仕方ない。
・安い喧嘩は買わない
このように自分の考え方を柔軟に変えたところ、同じような言動をされても怒らないようになり、むしろ笑ってスルーできるようになりました。
相手を変えるのがどうしても無理なら、自分が変わることにトライしてみましょう。
⑤まとめ
まとめます。
以上、ストレス・怒りのメカニズムからコントロール方法を紹介しました。
早速職場で実践して、ストレスを減らし楽しい毎日を過ごしましょう。
|
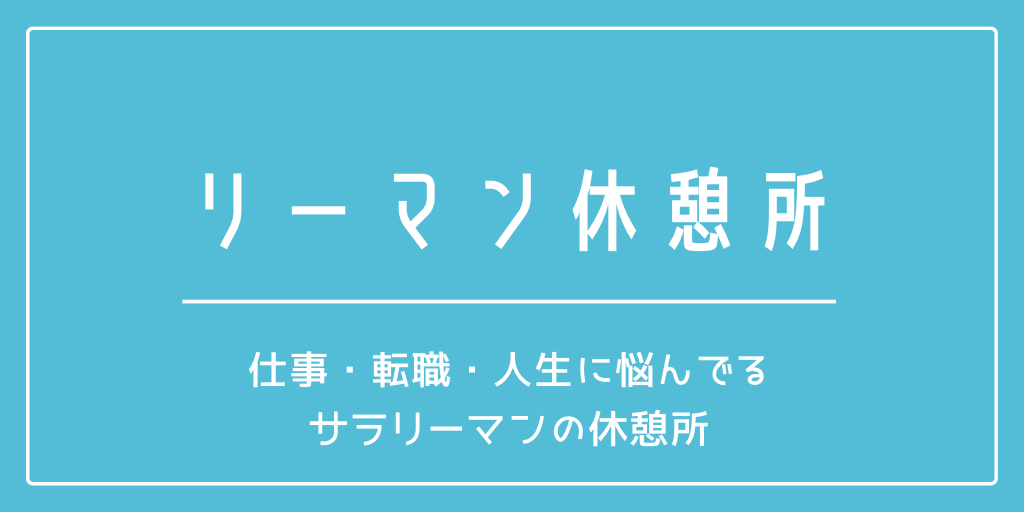
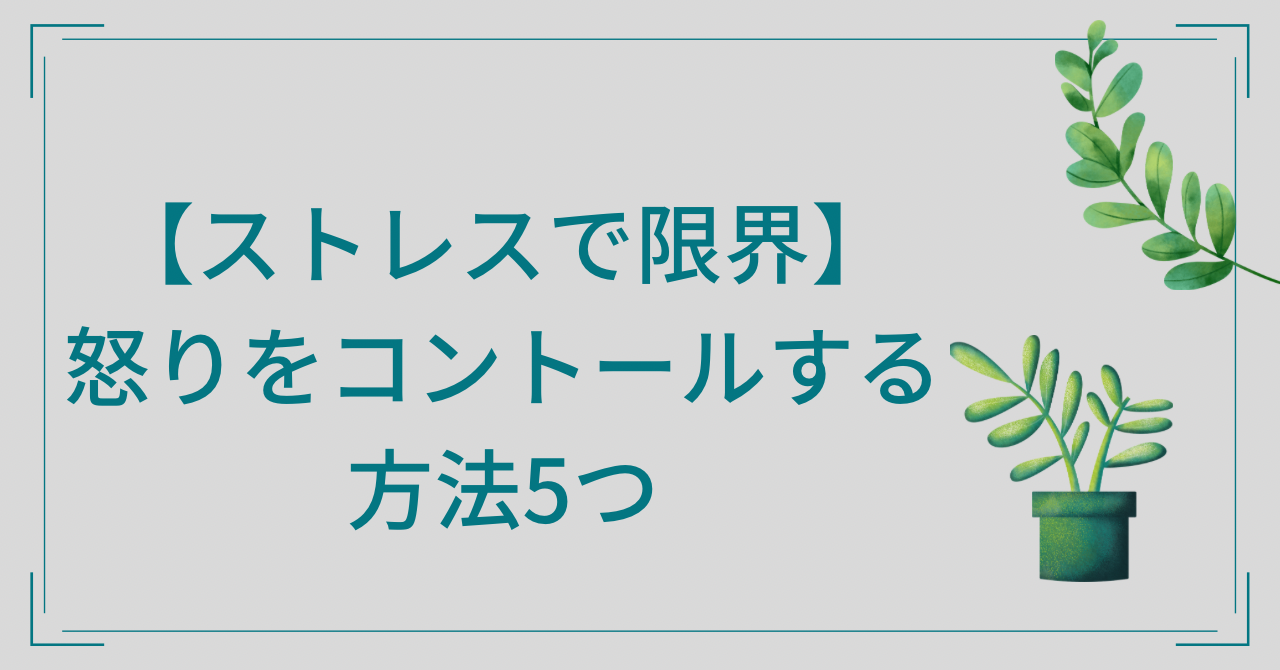
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1b795a22.43a6e025.1b795a23.09250b10/?me_id=1213310&item_id=19936806&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4206%2F9784532114206.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


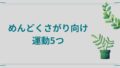
コメント